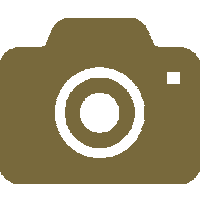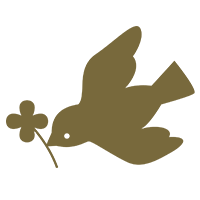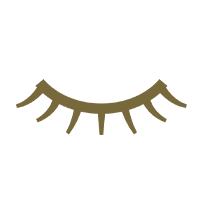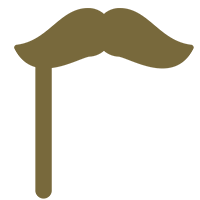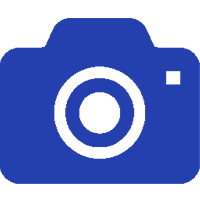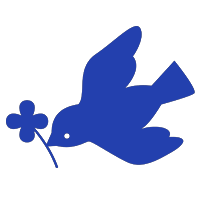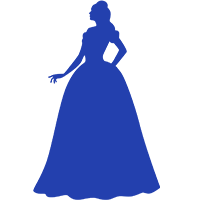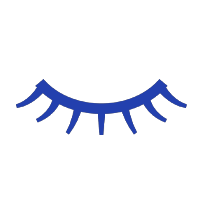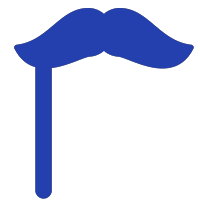取引先も結婚式に招待すべき?判断のポイントを徹底解説

結婚式のゲスト選びは、新郎・新婦が頭を悩ませるポイントの一つです。
取引先の招待については、仕事上の関係性やビジネスマナーを考慮し、慎重に判断する必要があります。
本記事では、取引先を招待すべきかどうかの判断ポイントや、招待するときの注意点をご紹介します。
ゲストリストに取引先を含めるべきかどうか迷っているカップルは、ぜひ参考にしてみてください。
取引先の担当者も結婚式に招待すべき?

結婚式に仕事関係の人を招待する場合、取引先も含めるべきなのでしょうか?
結婚式に仕事関係の人を招待するときの判断基準をご紹介します。
「呼びたいかどうか」より「呼ぶべきかどうか」が重要
結婚式に仕事関係の人を招待するカップルの多くは、「ビジネス関係を円満に保つため」「礼儀として必要だから」などを理由とすることがほとんどです。
「呼びたいかどうか」で考えれば「呼びたくない」と答える人も多く、単なる個人的な感情で決められるものではありません。
取引先の担当者を呼ぶかどうか迷ったときは、「呼ばなかったらどうなるか」を想像してみましょう。
「雰囲気が悪くなりそう」「仕事がやりにくくなりそう」と感じるのであれば、取引先の担当者も招待したほうが良いかもしれません。
一方、「特に困らない」「招待するとかえって迷惑になるかも」などと感じる場合は、ゲストリストから除外しても大丈夫です。
上司や先輩に確認する
結婚式を挙げると決まったら、まず上司や先輩に相談しましょう。
「結婚式に職場関係者は呼ばない」「取引先の社長まで招待する」など、企業の慣習は大きく異なるのが実情です。
先輩や上司のケースを踏襲すれば、大きな失敗を犯すリスクを避けられます。
企業の慣習的に取引先を呼ぶのであれば、ゲストリストには取引先の担当者も含めて置いたほうが無難です。
結婚式に取引先の担当者を招待するときのポイント

結婚式に取引先の担当者を招待するときは、招待状の渡し方や席次について配慮が必要です。
ビジネスに基づく関係だからこそ、結婚式に招待するときは細心の注意を払いましょう。
結婚式に取引先の担当者を招待するときの「ポイント」をご紹介します。
招待状は相手の会社宛に出す
取引先の担当者と個人的な付き合いがない場合、結婚式の招待状は会社宛に送るのが一般的です。
封筒の表面には会社の郵便番号・住所・会社名・相手の肩書き・相手の名前を正しく書きましょう。 結婚式の招待状を送るときに注意したいのは、正しい名称・漢字を使うことです。株式会社の場合は「(株)」と省略せず、「株式会社」と書くのがマナー。
相手の名前についても正しい漢字を確認し、正しいフルネームを記載してください。
招待状出す前に確認を取る
相手の名前や住所は名刺で確認できます。
とは言え、名刺交換から時間がたっている場合は、情報が変わっているかもしれません。
取引先の担当者に結婚式の招待状を送ると決めたら、肩書きや住所について本人に確認するのがおすすめです。
メールに相手の住所や肩書き・名前を書き、間違いはないかチェックしてもらいましょう。
ただし、ビジネスでのみつながっている人にいきなりメールを送ると、「礼儀を知らない人」という印象を与えるかもしれません。
メールを送る前に電話をし、「確認のメールを送付させていただいてよろしいでしょうか?」と伝えておくことが大切です。
招待状を送るときの工夫については、以下の記事も参考にしてください。
「招待状にはせっかくだから郵便局で風景印を押してもらおう☆」
⇒ ご覧ください。
手渡しならより丁寧な印象になる
上司や目上の人・大切な人を結婚式に招待するときは、手渡しが基本です。
相手の会社に行くことがある・相手と自由に会える状態であれば、対面で結婚式の招待状を渡しましょう。
招待状を手渡しするときは、封筒に住所を書くのはマナー違反となります。
表面には相手の名前のみを記載してください。
本人がその場で招待状を確認できるよう、封筒への糊づけも避けるのがマナーです。
差出人の住所・名前は書いておく
手渡しでも郵送でも、結婚式の招待状には「差出人の住所」と「名前」を書くのが基本です。
結婚式の主催者の住所・名前を記載しましょう。
結婚式の主催者は、主に次の2パターンがあります。
どちらを選ぶかは、新郎・新婦や両家の考え方・しきたりに合わせてください。
- 新郎・新婦名義:カジュアルな結婚式
- 両家の親名義:大規模な結婚式・格式を重視する結婚式
現代の結婚式では、新郎・新婦の名義を書くケースがほとんど。
両家の親名義にするのは、「家同士」の結び付きを強調したい結婚式です。
この他、「親に挙式代を出してもらった」などの場合は、親子連名にするケースもあります。
結婚式に招待する人を選ぶときの注意点

ゲストの顔ぶれによって、結婚式の雰囲気は大きく変わります。
新郎・新婦が思い描く理想の結婚式を実現できるよう、ゲストリストは慎重に作成することが大切です。
結婚式に招待する人を選ぶときの「注意点」をご紹介します。
招待する人をカテゴライズする
招待するゲストを決めるときは、候補者を親族、友人、職場関係者などのカテゴリに分けておきましょう。
カテゴリごとに関係性の深さ・招待の必要性の高さで優先順位を付けていくと、招待したい人が漏れたり、招待しなくても良い人を招いてしまったりするリスクを低減できます。
結婚式に取引先の担当者を招待する場合、自社の上司や先輩を招待しないと筋が通りません。
しかし、ビジネスカテゴリのゲストが多過ぎると、結婚式が堅苦しい雰囲気になる恐れもあります。
ビジネス色を強く出したくないときは、角が立たないように人数を調整しましょう。
自分で決められないときは、職場の先輩や既婚の同僚などに相談してみてください。
両家のバランスを考慮する
結婚式のゲストを選ぶときは、新郎・新婦間でゲストの属性の偏りが出ないのが理想です。
「新郎のゲストは仕事関係者ばかり」「新婦のゲストは友人ばかり」では、ゲスト同士の会話も弾みにくくなります。
なるべく近い属性でそろえると、式場全体の雰囲気も盛り上がりやすくなります。
ゲストの数については、新郎・新婦で違っても問題はありません。
ただし、両家の親や新郎・新婦自身が気になる場合は、ゲスト数も揃える方向で調整するのがおすすめです。
一番大切なのは「自分たちの気持ち」
結婚式は新郎・新婦にとって人生の新しい門出となるセレモニーです。
体裁や義務感でゲストを選ぶと、後悔が残る式となるかもしれません。
招待するゲストを選ぶときは、「大切な日を一緒にお祝いしてほしい人」を優先しましょう。
新郎・新婦が招待したくないのなら、無理に職場関係の人を招待する必要はありません。
会社に挙式の予定を伝えるときは「結婚式は身内だけで行う予定です」と伝えてください。
結婚式に招待するゲストの人数の決め方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
「結婚式のゲスト人数の平均や内訳とは?人数ごとの雰囲気や確定期限について」
⇒ ご覧ください。
結婚式に取引先を呼ぶかどうかは2人の気持ち次第
取引先の担当者を結婚式に招待するかどうかは、新郎・新婦の気持ち次第です。
ただし、取引先の担当者を呼べば、その分職場関係者の数が増えます。
カジュアルな結婚式にしたい・アットホームな結婚式にしたいなどと考えている新郎・新婦は、「取引先の担当者は呼ばない」という選択肢もあります。
まずは2人の理想の結婚式をイメージし、ゲストの顔ぶれを決めてください。
Otokuconでは、これから結婚式を挙げるカップルに向け結婚式プレゼントキャンペーンを実施しています。
簡単なアンケートに答えて当選したカップルは、「最大約70万円相当の挙式代が無料」になるチャンスです。
ぜひこの機会を利用して、理想の結婚式を挙げてください。